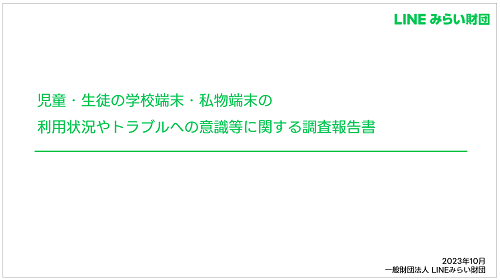調査・レポート
「児童・生徒の学校端末・私物端末の利用状況やトラブルへの意識等に関する調査報告書」を公開
2023.10.23
一般財団法人LINEみらい財団(以下、LINEみらい財団)は、GIGAスクール構想※1の中で活用が進んでいる学校端末※2および私物端末の利用状況等について、小学生と中学生を対象とした調査を実施しましたので、その結果をまとめた調査報告書を公開します。
本調査は、今後の情報モラル教育のあり方を検討する目的のもと、小学生と中学生に対し、学校端末・私物端末それぞれの利用状況や、端末利用時のトラブルへの意識についてアンケートを実施したものです。調査報告書では結果の分析に加え、本調査の監修を担当した明星大学教育学部 准教授 今野貴之氏の考察・提言についてまとめています。
■調査サマリー
- 私物端末を持つ時期が早いほど、安全な使い方を学んだことのある児童・生徒が多い
- 私物端末利用ルール等の見直しを行わなければならないと�考える児童・生徒は1割から2割程度
- 学校端末で困った経験や他者を困らせた経験があると答えたのは1割程度の限られた児童・生徒
- 端末利用時にトラブルが発生した際の対応がわからないと回答した児童・生徒は1割から2割程度
- 家庭において端末利用ルールがない児童・生徒のほうが端末の利用時間が増える傾向にある
■考察・提言サマリー
- 家庭によって私物端末の所持時期や安全な使い方を学ぶ機会が異なる中、私物端末について教員からの直接指導は現実的ではなく、学校と家庭のコミュニケーションや連動性を高めることが重要
- 学校においても学校端末の利用を通して私物端末の使い方や情報モラルを意識させていくことは可能。特定の教科や時間を設定して指導するという考え方ではなく、すべての教科において進めることが必要
- 学校端末を使った児童・生徒の学ぶ機会を増やすため、家庭の理解を得たうえで家庭への持ち帰り制限をなくし、利用機会を増やすなど、学校・自治体の学校端末利用ルールを見直しする活動が考えられる
- 私物端末利用の見直しを行わなければならないと考える児童・生徒が一定数いるが、児童・生徒自身が学校端末・私物端末の利用状況を「可視化」し、今後起こりうる問題を想像し「自分ごと化」できる環境を整備することが求められる
- トラブルの対処方法がわからない児童・生徒が一定数いる中、事前のトラブルのロールプレイや解決方法の体験はトラブル予防のひとつとなると考えらえる
- 学校側から保護者に対し、家庭でルールがないほうが私物端末の利用時間が増える傾向などを示し、家庭でのルール作りの大切さ、ルールの決め方を考えることを保護者面談などで促すことが考えられる
■調査概要
・調査対象
小学4~6年生(3校)、中学1~3年生(2校)
・有効回答数
小学生673名、中学生478名
・調査時期
2023年1月~3月
・調査協力
金沢大学附属小学校 / 金沢大学附属中学校
杉並区立天沼小学校 /杉並区立天沼中学校
上越教育大学附属小学校
・調査監修
明星大学 教育学部 准教授 今野貴之
■報告書データ
※1 文部科学省「GIGAスクール構想について」https://www.mext.go.jp/a_menu/other/index_0001111.htm
※2 本調査報告書では、学校で配布される端末を「学校端末」と呼称しています